時間を創り出す
初のメキシコ遠征以来、ソンブレロを頭に装備していたら、自分の中のラテンの血に火がついたのか、いろいろ考えて書いたり描いたりする時間に費やすことにしている。 秋の夜長というのはクリエイティブに過すのに適している。 論文を書いたり、ブログが炎上したり、鉛筆画を描いたり、奥さんとデートとしたりもしている。 もちろん仕事もしておる。今日はこのブログを沼津から書いている。 https://twitter.com/o_ob/status/670137613546688512 「忙しい」とは心を亡くすと書く。「師走」はその文字のとおり、先生が走ると書く。 忙しいのは当たり前であり、12月に先生が「時間が無い・時間が無い」と言って挨拶や酒ばかり飲むのも「当たり前」のことである。 本当のクリエイティブとは「時間を創り出す」こと、と教えている。創造者とはそうあるべきだ。 費やす時間が無くなれば、どんなスキルを持っていても、ただの「忙しい人」だ。 時間を創り出せ、そうすれば創れる。
落合陽一氏に書籍「魔法の世紀」の書評を頼まれた
そんなメキシコ遠征直前のある日、Facebookメッセンジャーでこんなメッセージが届いた。 白井先生 <略> 11/27(金)に初めての単著である『魔法の世紀』という本を刊行することになりました。 「映像の世紀」から「魔法の世紀」へというテーマで、今この世界で起こりつつある変化の本質を、テクノロジーとアートから語った1冊です。帯文は、富野由悠季監督、堀江貴文さん、チームラボ猪子寿之さんに寄せていただき、また、装幀は鈴木成一さんにお引き受けいただくことができました。 <略> この手の固い本(コンピュータ史やデジタルカルチャーなど)が売れることはあまりないのですが,一気にSNS上に本の情報を溢れさせることで、コンピュータ文化やHCIに世間を巻き込んでいきたく考えております! <略> 落合陽一 http://www.amazon.co.jp/gp/product/4905325056 
落合陽一と白井暁彦
この場を借りて、落合氏と私の関係を話しておく。私はいつも”落合君”とお呼びしているが、今は筑波大学の先生であるから”落合先生”とお呼びするべきで、しかも落合くんを”先生”と呼ぶと個人的には侮蔑や嘲笑に値する感じがなぜかするので表記上”落合氏”とする。 https://twitter.com/o_ob/statuses/512393856453591041 2014年9月18日(木)は氏の誕生日だったらしい。日本VR学会大会@名古屋大学にて。このときはたしか、落合氏が米国のマイクロソフトリサーチのインターンシップから帰ってきた日で、名古屋にたどり着いたけど日本円をまるっきり持っていないので、会場のレストランでご飯をご馳走してあげた記憶がある。 初めて落合氏にちゃんと会ったのも、確かそこから4年前の2010年 9月16日(木)あたり。金沢工業大学・日本VR学会 第15回大会だったと記憶している。私が日本科学未来館での非研究者としてのポストから、学壇に戻って初めての日本VR学会で、多重化隠蔽技術に関する初めての学術発表行い、エキサイティングなディスカッションを東北大学の北村先生と交わした。発表も終わった会場で、共著者である東工大・長野光希らと研究に関する反省会を行った後だっただろうか。懇親会に向かおうかという閑散とした会場に、落合陽一はいた。 大学3年生が学会にソロ参加している時点でも面白いな、と思ったのだけれども(長野君も当時3年生だった)、IPA未踏ユースプロジェクトで採択された「電気が見える」デバイスとソフトウェアの開発について、目の前でいろいろ見せてくれた。 「電気が見えるデバイス」は、何が面白いかと言われると、一言で説明するのが難しい。要素がいっぱい詰まっているな、と感じた。直感的に分かりやすいものを作っているけれども、そもそもどうして電気を見えるようにしたいのか?というモチベーションに興味が行った。予算獲得の説明にあるような「理科離れ」とか、単にかっこよく見せたいとか、そういう他のプロジェクトや作り手とは違う、「野生」のようなものがこの人物には感じられた。落合氏の白黒をベースにした独特の風貌のせいだけではないが、一要素ではある。 [caption id=”” align=”alignnone” width=”723”] Horiemon.comより[/caption] 私も野生の生き物なので、野生の勘を感じつつも、アホみたいに「お父様が国際ジャーナリストの落合信彦なんだってさ~」という紹介で、これまた懇親会場で近くに居た現代美術館の森山朋絵さんに紹介し、スーパードライを飲みながら盛り上がったことを記憶している。 https://www.youtube.com/watch?v=5QWzMWDCeOY お父様が国際ジャーナリストなのに、名前がプラスとマイナスで陽一とは、なんとカオスなのだろうか。 本人は「電気を見えるようにしたい」といっているし、 こんな白黒ファッションをしつけている、お母様は陰陽術士に違いない。 その後の私と落合陽一氏は「ジョナサン・ノマドワーク仲間」とでも表現できようか。 私が深夜・日中のジョナサンで「白井博士の未来のゲームデザイン」の執筆や、論文やコーディングをしている頃、ちょうど彼も似たようなことをしているから非同期遭遇率が多いのである。ジョナサンはドリンクバーもあるし、シートが柔らかく、机も広いので、執筆向きなのである。 朝の3~4時ごろのTwitter上で出くわすことが多い。 https://twitter.com/o_ob/status/394382735139028992/ もちろん最近は私は徹夜をしないようにしているし、テレビやメディアでの露出が多くなるとジョナサンで仕事していると一般の人に声を掛けられてしまったりするので、悩ましい。
Horiemon.comより[/caption] 私も野生の生き物なので、野生の勘を感じつつも、アホみたいに「お父様が国際ジャーナリストの落合信彦なんだってさ~」という紹介で、これまた懇親会場で近くに居た現代美術館の森山朋絵さんに紹介し、スーパードライを飲みながら盛り上がったことを記憶している。 https://www.youtube.com/watch?v=5QWzMWDCeOY お父様が国際ジャーナリストなのに、名前がプラスとマイナスで陽一とは、なんとカオスなのだろうか。 本人は「電気を見えるようにしたい」といっているし、 こんな白黒ファッションをしつけている、お母様は陰陽術士に違いない。 その後の私と落合陽一氏は「ジョナサン・ノマドワーク仲間」とでも表現できようか。 私が深夜・日中のジョナサンで「白井博士の未来のゲームデザイン」の執筆や、論文やコーディングをしている頃、ちょうど彼も似たようなことをしているから非同期遭遇率が多いのである。ジョナサンはドリンクバーもあるし、シートが柔らかく、机も広いので、執筆向きなのである。 朝の3~4時ごろのTwitter上で出くわすことが多い。 https://twitter.com/o_ob/status/394382735139028992/ もちろん最近は私は徹夜をしないようにしているし、テレビやメディアでの露出が多くなるとジョナサンで仕事していると一般の人に声を掛けられてしまったりするので、悩ましい。
メディアアーティストとしての落合陽一
私は工学者としての側面からメディアアートを教えることが多い。 メディアアートは「ニューメディアアート」として語られたり、{媒体,コンピュータ,ガジェット,ネットワーク}アート、「科学と芸術の融合」と語られたりする歴史があるが、エンタテイメントシステムを研究する私は、ここ数年「メディアアートは人と人との関係性を創るアート」として説明してきた。 そういえば、私自身も東京工芸大学の学生の頃、アーティストを名乗っていた時代もあった。 しかし、写真であったり、イラストレーションであったり、マンガであったり、コンピュータグラフィックスであったり、映像であったり、ゲームであったり、バーチャルリアリティであったり、論文であったり、ジャーナリストであったり、そして工学者であったり、研究者であったりと、単なる「アーティスト」と自称するのは作品さえあれば問題は無いのかもしれないが、表現する「arts」が多すぎて、受け手の考える「アート」の枠では収まらない。なんとなくファインアートの人々に失礼な気もするし。 落合陽一は、たしかにガジェットを作ってはいるけれども、筑波大学にはいるけれども、明和電機や岩田洋夫先生、クワクボリョウタ氏に代表されるようなツクバ系デバイスアーティストとは何かが違う。 https://www.youtube.com/watch?v=Hmelkum5zAE https://www.youtube.com/watch?v=5t5NE9q–Sc https://www.youtube.com/watch?v=-dN_afUlGOI 私はエンタテイメントをまじめに研究する側なので、明和電機のようなエンタテイメントは大好きだ。しかし、落合陽一は自己表現のためにアートをやっているのは間違いないが、他の自己目的性のアーティスト、つまり「表現したいからやっている」という自己目的性ではなく、何か別の目的があることを感じる。 何が違うのかは、このブログアーティクルの中で、書評とともに、分析していきたい。
落合氏は「現代の魔法使い」、私は「錬金術師」。
落合氏は自分のことを「メディアアーティスト」とは名乗らず「現代の魔法使い」という通り名でセルフプロデュースしている。メディアもそのいでたちと響きをうまく受け止めているようだ。 自分が2010年から研究している多重化隠蔽映像技術も、多くの人が体験したときに「魔法だ!」という反応を示す。 https://www.youtube.com/watch?v=lOMx5F7aGEQ 電気的な道具を使わずに、偏光だけで、かつ何の改造も施していないディスプレイが多重化する。見ている映像がフィルタを通してみた場所だけが異なる体験に、人々は「魔法」を感じる。多くの人々は技術的な説明を聞きたがる。私も科学コミュニケーターの端くれなので、説明はするが、アルゴリズムの細かい話をしても納得する人など居ない。そもそもそんな質問をするのは電機メーカーのエンジニアか、研究者ぐらいで、酷いときにはさんざん説明した後に「わかった!これで別の特許が出せそうだ!」なんて失礼なことを言い出す人も居る。優れた技術デモというものは、そうやって多くの人に別のアイディアを与えてしまう事をよく経験する。私は錬金術師なので、普通の金属をレアメタルに変えるような技術の創出方法には興味があるけれど、私自身のアイディアにインスパイヤされて出た特許など興味は無い。ただ、人々の頭の上に浮く「!」については、錬金術の材料として興味があるので展示などはできるだけ前に立っていろんな人に「!」の理由を聞き出したい。人によって、「納得した!」というラインは様々異なる。「技術が知りたいのではなく、納得したい」という人がほとんどであるので、時間が無いときは「魔法です」というと、「ああ!なるほどね!」と納得してしまう人も本当に居る(もちろん技術という魔法として解説するが)。 さて落合氏の話に戻る。落合陽一の名前を知らない人でも、この動画は見たことがあるかもしれない。 https://www.youtube.com/watch?v=odJxJRAxdFU これは私がチェアを担当しているフランスのLaval Virtual ReVolutionで展示された、音響浮遊+LEAP Motionによるデモで、これを体験するLavalの子供たちはまさに、魔法使いの体験だった。 Lavalでのこの写真を見ていると、落合陽一が「魔法使い」として具象化している。 https://twitter.com/ochyai/status/586398470354808833 実は「現代の魔法使い」との通り名は、ホリエモンこと堀江貴文氏が名づけたとのこと(落合氏の記録による)。ちょうどこの頃、私も堀江氏にインタビューされ、このイベント「ホリエモン春のVR/AR祭り@ロフトプラスワン」(2014/3/31)にも呼ばれて一緒に講演していたので、私は落合氏が「現代の魔法使い」として登場する過程を「ハコスコ」登場とともに、目の当たりに見届けていることになる。 https://twitter.com/o_ob/status/450626052801310720 https://twitter.com/o_ob/status/450626759394729984 落合氏が「現代の魔法使い」なら、私は「偏光の魔術師」とか「現代の錬金術師」でありたいと思う。私はお金に興味があるわけではないが、こなれた物質であるコンシューマーデバイスであるWiiRemoteなりKinectなり3Dディスプレイといった、当たり前のマテリアを金(キン,Au)に変えるような技術を研究するのが大好きだ。世の中は、「カネに変えたい人」は多いかもしれないが。
現代の錬金術師が、現代の魔法使いの書籍「魔法の世紀」を読む
魔法使いにしても錬金術師にしても、世間からは「ウサンクサイ」と思われるのが常である。私は魔術師でも奇術師でもなく、錬金術師なので、どうやったら普通の金属が価値のあるレアメタルになるのかを理解しているし、説明しろといわれれば納得のいく説明方法を用意できなくもない。落合陽一は「魔法使い」であるから、魔法を使う。魔法を作る方法もおそらく知っている。魔法使いの中には、魔法を使っているが作る技術がない者、魔女のように世間からの迫害を避け、隠遁生活を送る者も多く居るが、氏はそうではなく、自分で作るだけでなく、どんどんと衆目に向かっているようにも見える。 そんな落合氏が書いた「魔法の世紀」。 さて読み解いていこう。
「魔法の世紀」表紙と帯から
[caption id=”” align=”alignnone” width=”1577”] 「魔法の世紀」落合陽一[/caption] 表紙はLaval Virtual 2013でも展示された「コロイダルディスプレイ」。帯の解説もしておく。
「魔法の世紀」落合陽一[/caption] 表紙はLaval Virtual 2013でも展示された「コロイダルディスプレイ」。帯の解説もしておく。
情報技術がディスプレイの内側ではなくこの現実を変える時代、 「映像の20世紀」は終わりを告げる。そのとき社会と芸術は変化するのか。 その最先端を担う研究者にして、メディアアーティスト―― 28歳の<現代の魔法使い>が世界を揺るがす――。
富野由悠季: 現代の魔法使いの杖が古典に内在するアートを掘り起こし、新しい世界への道筋と在り様を語る。若さ故の語り落としもあるのだが、その心意気は憎くも愛したい。落合陽一はニュータイプだろう。
堀江貴文: コンピューターは僕にとって魔法の箱だった。そして魔法はまだとけないことをこの本で知った。落合陽一の魔法があれば、僕はあと50年は戦える
チームラボ猪子寿之: 未来を生きるすべての人々へ
富野氏の「落合陽一はニュータイプ」という言葉はインパクトがあるし、富野ファンにとって、あまりに汎用的な1行なため、単なる富野節というか、軽く聞こえてしまうかもしれない。しかし、本書を読んでみると富野氏のメッセージの前半のほうがはるかに意味がある。富野氏はなぜ落合氏の「心意気を憎くも愛したい」のか。 堀江氏は私と同世代なので、「コンピュータは魔法の箱」という視点は共感できる。そして「コンピュータの魔法がとけるんじゃないか」という疑念を抱いている。たとえば2015年現在のiPhoneや、今年登場したAppleWatchの存在は、まるでワクワクしない。「魔法がとける」という言葉は「解ける」つまり、種明かしをされてしまう、という意味もあるが、本書を読むと、これは「溶ける」と脳内変換するのが良いと思う(詳しくは本書内の八谷和彦氏の発言を参照)。「あと50年は戦える」という表現は1世紀の半分を意味するが、これは堀江氏の「我が闘争」を読まねば真意は分からないかもしれない。気になるのは「落合陽一の魔法があれば」の11文字で、これは帯を使った公式の投資オファーなのか、落合陽一氏が本書で語る「魔法」についての話なのか、未来の読者のために、解説はしないでおく。 猪子氏はひとこと。「未来を生きるすべての人々へ」。明らかに多読な堀江さんに比べ、猪子さんは本なんて読んでなさそうなキャラクターではあるけれど、この13文字で、かなりのことを語っている。帯は本当に文字数制限が多い。猪子氏はこういうとき、軽く天井のほうを見ながら目を閉じて、彼のスーパーコンピューターにアクセスして、突然ひとことで、こういうことを言う人物。私も、この13文字には同意する(結論で理由を述べる)。 帯と装丁で、ちょっとだけ残念なのは、この書籍がいったい何なのか? いわゆる 普通の人 には全くわからないことだ。 本を開けば縦書きだし、一般の書店流通を通していないらしいし。 Amazonで買うのが一番手っ取り早いが、装丁が美しいので手に取りたい魔術書ならではの魅力がある。おそらくこの書籍を店頭に平積みしている書店があるとすると、おそらくその書店は魔術書を好んで扱う書店に違いないからTwiterで落合氏に報告すると好まれるだろう。
「魔法の世紀」目次から
私自身の書評は本エントリーの最後のほうにまとめた。約束どおり、Amazonにもポストした。ここから書評が始まるかと思うと、読み手としてはクッソ長いブログですまないが、読みすすめてほしい。 以下、目次より抜粋する。ちなみに1章ごと1冊の本といえるぐらい、内容が濃く、テンポが速く、テイストが違う。
- まえがき
- 第1章 魔法をひもとくコンピュータヒストリー 魔術化する世界 コンピュータを〝メディア化”したアラン・ケイ 早すぎた魔法使いと世界を変えた4人の弟子 ユビキタスコンピューティングへの回帰
- 第2章 心を動かす計算機 なぜ僕は「文脈のアート」を作るのをやめたのか メディアアートの歴史を考える アートがテクノロジーと融合する コンテンポラリーアートの背景にある「映像の世紀」 「原理のゲーム」としての芸術 コラム メディアアートとしてのキャメロン作品
- 第3章 イシュードリブンの時代 プラットフォーム共有圧への抵抗 新しいことをするために なぜイシュードリブンの時代なのか コラム 人工知能は我々の世界認識を変えるか
- 第4章 新しい表層/深層 デザインの重要性 デザイナーの誕生─バウハウスの産声 表層と深層を繋ぐもの 表層と深層の再接続がもたらすもの
- 第5章 コンピューテーショナル・フィールド メディアの歴史 「魔法の世紀」における「動」の記述 コンピューテーショナル・フィールド コラム 計算機にアップデートされる美的感覚
- 第6章 デジタルネイチャー 「人間中心主義」を超えたメディア コード化する自然:デジタルネイチャー 場によって記述されるモノ エーテルから生成されるモノ 魔法の世紀へ
- 落合陽一 メディアアート作品紹介 2009〜2015 あとがき 画像出典一覧/ 引用文献一覧
“まえがき” を解説
まえがき「映像の世紀」から「魔法の世紀」へ p.12より引用する。
「映像の世紀」のまっただ中の1973 年に、SF 作家アーサー・C・クラークは、「充分に発達した科学技術は、魔法と見分けがつかない」という有名な言葉を残しました。 魔法とテクノロジーについて考えたときに皆さんが最初に思い浮かべるのは、この言葉ではないでしょうか。 研究者やエンジニアたちは、世の中に文字通りの「魔法」なんて存在しない、最初からあり得ないものと思い込んでいます。だからこそ、彼らはこの表現に巧妙さを見いだすのでしょう。しかし、僕はこの言葉を、単なるレトリック以上の可能性として捉えています。つまり、ありえないほどの超技術は、文字通りの「魔法」になりうるのではないか、と。 僕は「再魔術化」の果てにあるのは、まさにクラークが遺したこの言葉が実現した世界だろうと考えています。
余りにも有名なアーサー・C・クラークの「十分に発達した科学技術は、魔法と見分けがつかない」は実は3本法則あるうちの3法則目「Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic」で、私が好きなのは第1法則「高名だが年配の科学者が可能であると言った場合、その主張はほぼ間違いない。また不可能であると言った場合には、その主張はまず間違っている」だったりする。それはともかく、この時点で「魔法」とか「再魔術化」などの言葉が出てくるので、この本の読者であろう研究者はエンジニアたちは面食らうことに違いない。 この書籍を読んで、落合氏の技術やその発想のエッセンスを盗み取ろうと考えた人々は、まずここで降参する必要がある。頭を中学二年生ぐらい設定する必要がある。この本を読むときの心構えとして、私はあえて「この本はSF」として設定することをお勧めする。 なお、アート系の読者のなかでも特に哲学よりではなく能天気な読者は、何も考えずに2章から読み始めたほうがいいかもしれない。
「第1章 魔法をひもとくコンピュータヒストリー」 を解説
この章は、読む人にとっては面白い。 一方で、読む人にとっては、全く面白くない。 その評価は「世代」と「勉強への興味」によって分かれるかもしれない。 面白いであろう世代は1990年生まれ以降のデジタルネイティブ世代。 面白くないであろう世代は1960年代生まれのマイコンとともに育った世代だ。 私は1973年生まれなので半々の世代。 本章を面白くする、もうひとつの軸が「読み手の勉強への興味」、知的探究心だろう。 本章は完全に歴史書だ。ドラマはほんの少ししか含まれていない。 「歴史が好きだ」という人や「歴史を学ぶのが好きだ」という人で、それを知らない人にはワクワクする話だろうが、その歴史をリアルタイムで生きてきた人々、特に紹介される人物のライバルだった世代には面白くない歴史でしかない。富野氏の「語り落とし」はこんなところも見える。 本章は、おそらく「魔法の世紀」を明確にするため、20世紀を「映像の世紀」と定義するため、歴史書として配慮して書かれたものと思われる。 しかし構成上のつくりから面白いところも感じられる。 確実なことは、落合氏がアラン・ケイに特別な敬意を持っていること、だ。 「サザランドの4弟子」であるのに、別次元で扱っている事から読み取れる。 私もアラン・ケイには大きく揺り動かされたので、共感する。 ちなみに1章だけで、1冊のコンピュータ・インタラクションの教科書といえるぐらい、情報量が多く、かつテンポが速い。 落合氏が、学生時代にノートに書いていたことをそのまま再構成したのではないかと思うような知識量と、歴史の再構成がなされている。 クラスの優秀な人物のノートをテスト前にコピーさせていただくような表現で申し訳ないが、 これをそのまま教科書として使いたい。 メディアアートやコンピュータの歴史を教える教員にだけ(こっそり)教えておく。
「第2章 心を動かす計算機」を解説
第2章も歴史が続く。しかしこの章は第1章と比べると、ドラマチックだ。 おそらく第1章は工学系の読者に配慮したもので、歴史上の事実を圧倒的な情報量とその整理をもって圧倒し、最後に「Pixie Dust」に至るまでの道筋を必然とするために必要だったものと考える。 しかしアートを批評するものは主張、能天気なクリエイタは主観と技法で物事を判断する。第2章はそれらすべてをドラマチックに巻き込んでいく。 余談ではあるが、まず嬉しくも複雑なのは、落合氏は、まぎれも無く「メディアアートで育った世代」であるということ。幼少期の写真や体験などはテレビ番組などで特集されているので知ってはいた。たしか電話を破壊している。私の場合は、時計を破壊(主観では「分解して再度組み立てに失敗」している)、母の大事な高級腕時計をより美しくするために食洗機にかけて破壊したこともある(私は母が生きているうちにオメガを弁償せねばならない)。「電話」というデバイスは、私は分解対象にはしなかった。黒電話はたしかに魅力的ではあったけれど、通話は有料なので、子供が自由に触ってはいいものではなくリカちゃん電話や110番といった禁断の遊びに近かった。私はそういう少年時代であったが、落合氏は少年時代にMIT石井裕先生の「タンジブルビット」の展示に出会っている。石井裕は電話会社NTTの研究員だった。メディアアートの美術館である初台icc(インター・コミュニケーション・センター)もNTTの資本で創設された。「Demo or die」のMITメディアラボ、数ある石井裕の作品・技術デモの中でも、「ミュージックボトル」という「タンジブル・メディア」の中でも比較的難解な原理的メディアアートがきっかけになっていることを知れて興味深い。 筑波大学に滑り止めで受かった落合氏は、すでに紹介した日本を代表するメディアアーティスト、クワクボリョウタや八谷和彦といった人々に直接影響を受ける。 個々の出会いのドラマについては本書を楽しみに読んでほしい。 以下は、iPhoneとの出会い。
僕も当時、さっそくiPhone を手に取ったのですが、その便利な機能を使ううちに、はたと考えこんでしまいました。こんな凄いデバイスが普及していったら、人間はコンピュータの下位の存在になってしまうのではないかという疑問が生まれたのです。
なるほど。落合氏でもそう感じることもあるのか。 問題はその後で、きわめて中二的な思想世界が展開される。
コンピュータの総体が、ひとつの意思や特殊なエントロピーのような性質を持っているのではないかと考え始めたのはこの頃です。 人間とコンピュータのどちらが主体なのかを。 生物学の知識がある人は、ミトコンドリアは元来独立した生物だったのに、自身を効率よく複製するために真核生物と共生を始めたという説を知っていると思います。 同様に、人間も自分たちをより確実に生存させるべくコンピュータを使っているうちに、気がつけばコンピュータにとってのミトコンドリアになっていくのではないか ─ふと、そう思ったのです。なかなかにクレイジーな考えかもしれないですが ……。
わかるわあ。 私の青少年のころは逆で、コンピュータがミトコンドリアになって人類に組み込まれる可能性を感じたものです。まだ実現していないけどバイオコンピュータとか。
当時の僕は人間がコンピュータのミトコンドリアになる未来を、世の人々に受け入れさせるべく人間の自己認識を問うような作品を作っていました。この考えは現在では少し変わっている面もあるのですが、その後の研究にまで繋がる大きなテーマになっています。
氏の「文脈のアート」作品の中でも最もインパクトがある作品は「ほたるの価値観」だろうか。 https://www.youtube.com/watch?v=xU8WPIzKSyA 氏が「ほたるの価値観」に至るまでに昆虫を殺しまくって以降、「視野闘争のための万華鏡」や「サイクロンディスプレイ」を作っていた頃、この転換が訪れる。
その後、僕は本格的にメディアアートの作品に接近していきます。当時、特に興味を持っていたのが、人の認識の解像度の問題について錯視を用いて迫った作品です。 この問題を考えるキッカケになったのは、またしてもApple 社です。その頃に発表された超高精細のRetinaディスプレイが、人間の網膜では区別がつかないレベルの解像度だと話題になっていました。ところが、ちょうどその時期に、僕は『貴婦人と一角獣』という世界最大級のタペストゥリーを見る機会がありました。その巨大な絵の前に立っているときにふと、これは全て刺繍で作られているのだから、縦糸と横糸をピクセルと解釈すれば、Retinaよりずっと解像度が高い世界最高のピクセル表現と言えるのではないかと考えていました。
そう。 「Retinaは網膜って意味だぜ」「だから網膜の分解能より高いんだぜ」って言ってる連中を、「はあ?何いってんの?」と一蹴してしまうのがただの工学者や理学者の発想と行動だが。
人間の目の分解能と空間の本質的な解像度の対応は正確に言えばディスプレイのピクセルの細かさで判断するのは難しい(例えば星の光は解像度というよりは光子が眼球に飛ぶこむことによる対応関係で考えた方がわかりやすい)のですが、そんな風に解像度という言葉を拡張 していくと、現実世界はある意味では無限に解像度が高いディスプレイであるとも考えられます。そして、この無限に解像度が高い錯覚の信号からイメージを生成できれば、それは現実と変わりがないのではないかと考えたのです、そういった現実性の再定義みたいなものを作品として作っていくことも面白いなと思っていました。
最近私はこれを「Real Virtuality」と呼んでいます。 氏は、続けて文脈のアートからの転換を書いている。
最近の僕はいわゆる文脈的な作品をほとんど作っていません。代わりにメディア装置の研究ばかりしています。 これは大学の研究者とアート活動を往復する中で、あることに気づいたのが理由です。どうやらメディア装置の制作による「表現」という試みと、メディア装置の「研究」はよく似た特徴を持っている─そんなふうに思うようになったのです。 この僕の結論はあまり理解されないかもしれません。なぜ新しいメディア装置の研究がメディアアートの表現になるのか─怒る人もいそうです。
「デバイスアート」が何であるのか?を世間に伝えるために、日本科学未来館で1日3,000人ぐらい来るお客さんに、科学を伝えていた私(科学コミュニケーター)からすると、怒るというより、このような青年が登場してくれたことに安堵を覚えざるを得ない。世の中はいまだに「科学と芸術は相容れない」なんてことを当たり前のように考えている一般の人や、企画者にあふれているのだから。 続く「原理のゲーム」としての現代芸術の解釈、歴史も大変役に立つ。 ちょうど昨日、2015年の11月27日に発売されたばかりの書籍なので、書籍の全てを分解してしまうのは誰にとっても嬉しくない。続く章も解説していきたいが、それは読むものの自由を奪う行為になるので、今日はこのへんでやめておく。いつか追記するかもしれない。 2章の中で、ひとつだけ、紹介しておきたい図がある。「うなずきん」だ。  落合氏はこの「うなずきん」を相手に涙している。
落合氏はこの「うなずきん」を相手に涙している。
書評:落合陽一は「現代の魔法使い」ではない、魔法使いを名乗る「未来人」である。
この本を読んでいて、私の中での「ある仮説」が確証付けられていった。 落合陽一は「現代の魔法使い」ではない。 魔法使いを名乗る「未来人」である。 理由がいくつかあるが、端的に紹介しておく。 歴史について詳しい上に、整理されすぎている。この本はSFでありFuturology(未来学)の本だ。私も「白井博士の未来のゲームデザイン」で未来学を書いたので、Futurologistの端くれなのかもしれないが、人類が現代まで築き上げてきた知識と経験を、現代の子供が28年間の間に効率よく学んだとしても、ここまで整理をして凝縮して伝えるのは難しい。一方で「魔法の世紀」を生きている未来人が、何らかの事故で「映像の世紀」に産み落とされてしまい、未来人の観点から過去の歴史を整理していると考えれば腑に落ちるし、「魔法の世紀」からみた歴史上の重要でない事項を語り落としたとしてもあってしかるべきだ。父・落合信彦氏も「2039年の真実」を書き、Wikipediaによるとブラックマンデーの直前にはドナルド・トランプに「売り」の指示を出して大統領候補の大富豪トランプの損害を大幅に救ったことがあるそうだから、実は家族そろって未来人一家なのかもしれない。 超時空要塞マクロスに乗って宇宙を地球に向かって漂流している未来人にとって、メディアアートは原理と文脈のゲームでしかない。 フェムト秒の時間で世界を観測している未来人にとって、物質は「窓」でしかない。 未来人であることは、さすがに秘密にしておいたほうがいいので、 魔法使いを名乗って、それで世間をカモフラージュしているのだろう。
「命を削って書きました」
https://twitter.com/ochyai/status/665166481701781505 落合氏が未来人であるかどうかの正体はともかくとして、彼は現代に生きている。ご自身がつぶやいておられるように、この書籍は「命を削って」書いている。私も落合氏も同じであると思うが、博士論文も命を削って書いているし、テレビ番組だって命を削って出演している。Twitterにおけるつぶやきだって、そうだ。ただの大学生だった落合君は、博士になり、いまや日本を代表する魔術師になっているが、彼の削命行為は衰えるどころか、ますます輝きを増している。
なぜリスクをとり 命を削るのか
氏は、最近、筑波大学の助教に着任された。大学1年生から研究室に出入りする学生を巻き込み、こんな活動をされている。 <落合陽一×SEKAI NO OWARI>ライブ会場に「魔法」をかける〜Zepp DiverCityを大改造! 安全なところで、時間もかけずに、リスクもとらずに先生面していることだってできるのに、あえてホコリまみれになり、高所に登り、作業をする。しかもこの作業には私の知るところでは大学1年生の教え子たちも参加している。このようなリスクをとり命を削る本当の目的とは何か。それは「育ってほしい」からではないだろうか。いや、正確には育った後に「次の世紀に進んでほしい」に他ならない。馬鹿のふりをする、誰もやらないことをやる、面倒なことに時間をかける。それらはすべて「自分がやりたいからやる」のではあるけれど、そのような馬鹿を単身でやること事態に相対的な価値などない。社会に対して発信する意味があるのは、それを背中で示す必要があるからではないだろうか。 私は落合氏の考える世の中観は当初(書籍を読むより、ずっと前)、非常に荒っぽくナマイキな感じがしたけれども、それは19世紀末の人間が20世紀の人間を見たら、誰でもそう感じるだろう。未来から来た未来人なのだけど、何かの理由で未来と現代を行き来することはできないから、苦悩している。未来にはどんな病気も治す薬などもあるかもしれないが、現代では入手できないから意外な苦労もするだろう。前世代の古代酒をうかつに口にして壊れることもあるだろう。そうやって思わぬところで死線をさまよい何かを悟った後に、「命を削って研究をすることの意味や覚悟」をよく理解していて、私は共感している。それは本書の中では「モチベーション」として表現されている。「コンピュータになくて人間にあるもの」、それは「やる気」であると。 過去には「根性」と呼ばれていた時代もあったが、未来人であってもそれは変わらないようだ。 人工知能がいくら進化しようとも、研究者にとって、研究はライフ(Life: 人生、生活、一生、活力…)であり、「モチベーション」だけが人間の存在価値なのだ。
落合氏はどこに向かうのか
人工知能に関するコラムで、氏は興味深い「最高の未来」を語っている。 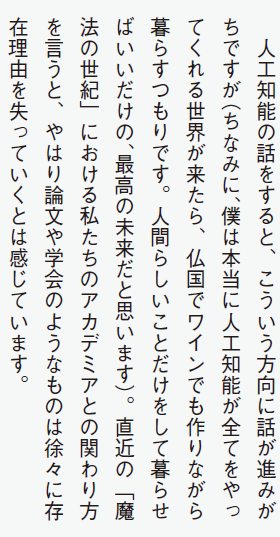
「コラム 人工知能は我々の世界認識を変えるか」(p.123): 人工知能の話をすると、こういう方向に話が進みが ちですが(ちなみに、僕は本当に人工知能が全てをやっ てくれる世界が来たら、仏国でワインでも作りながら 暮らすつもりです。人間らしいことだけをして暮らせ ばいいだけの、最高の未来だと思います)
後半のアカデミアとの関わり方は未来人が言うのだから仕方ない。 最近は温暖化の影響でワイン産地もだいぶ北上していて、近い将来にはロワール川北側のLavalでもワインが作れる時代が来るかもしれない。 「魔法の世紀」の普通の人たちの暮らしは、フランスの田舎にある。
おわりに
私の長々とした人物紹介と書評を読んでくれてありがとう。 このすばらしい書籍を現代にプレゼントしてくれた落合陽一氏にまずは拍手と喝采を浴びせなければならない。 御礼のかわりに、Amazonには以下のようなショートレビューを書こうと思う。
「十分に発達した魔法使いは、未来人と見分けがつかない」
本書は工学書であり、美術書であり、メディアと現代美術の歴史書であり、サイエンスフィクションである。 落合陽一は「現代の魔法使い」ではない、魔法使いを名乗る「未来人」である。 2015年、歴史の大車輪において、 「映像の世紀」である20世紀の様々な輪廻が起きている。 「魔法の世紀」に生きている落合氏にとって、 iPhoneは人間の存在価値の喪失と悟りを与えるきっかけとなる装置であり、 バーチャルリアリティやメディアアートは必然であり、 それは世の中に溶け、Kickstarterでの資金集めも、 その輪廻の一部でしかない。 この輪廻を脱し「魔法の世紀」に進むためには、 我々はこの本を年内に読み、未来から過去に向けて、 前世紀の重力圏を脱しなければならない。 このような「魔術書」はなかなかお目にかかることはできない。  https://twitter.com/o_ob/status/671079802908971008
https://twitter.com/o_ob/status/671079802908971008